
原幹公認会計士事務所
エンジニア・クリエイターのための会計事務所です。会計やICTに関連したトピックを書いてます今年も3月15日が過ぎていきました。みなさま期限内に提出完了しましたか?

まだ自分の作業も完全に終わったわけではないですが、今年の確定申告シーズンのふりかえりなどをやってみます。
- マイナンバー普及の道は遠かった
今年から申告書類にマイナンバーの添付が必要になりました(マイナンバーカードのコピーまたはマイナンバー通知カードのコピー+本人確認書類の写し)。これが実に集まらない集まらない。マイナンバーカード自体は全国での作成率が10%を切っているので作られてないのは当たり前として、通知カード紛失(見当たらない、保管したけど行方不明など)多数発生。当初は書留など追跡可能な手段で郵送してねと依頼するも次第にルーズになり、FAXやスマホ画像などで送ってくる方も多数。いいのかこれでと思いつつ申告資料を仕上げました。
もとよりマイナンバーは普及するのはいろいろ無理がありそうなので(カード作成の煩雑さなど)このような展開も無理もないとはいえ、来年も同じような煩雑な運用になると思うと気が重いです。もともと税や社会保障の手続を効率化できるはずだった制度なのに、なぜこのような状況になっているのでしょうか。
- 進捗状況の可視化は徹底すべき
「一人スクラムをためしてみた」でも書きましたが、今回はスケジュールや作業進捗状況を意識的に可視化するよう心がけました。これはなかなか効果的で、遅々として進まないようにみえる申告作業も少しずつ進むことが実感できます。翌朝になればその日に何をやるかがクリアになるので、このテクニックはかなり有効に感じられます。タスクをより細かく分解することで進捗状況をより細かく管理できることも今回実感できたのは収穫でした。
- スケジュール調整はやはりうまくいかない
とはいえ、申告作業のように「資料が断片的に集まる」→「申告資料に反映する」→「確認する」→「最初に戻る」のサイクルを繰り返すのは非効率と思いつつも、こればかりは相手あっての作業になるのでなかなか思い通りのスケジュールで進みません。前年度の反省を踏まえて依頼資料一式をあらかじめ準備し、収集状況を管理するのを徹底したとしても結果はあまり変化なし。2月-3月の混沌としたスケジュールとそれにともなうもやもやからは解放されるのは難しそうです。
- 収集資料をいかに一元管理するかが課題
収集資料が電子データで送られてくるケースが増えてきましたが、それらを一元的に管理する仕組みがまだまだ確立できていません。メールのファイル添付は取りこぼしやすく要注意なので、やりとりするファイルを一定の場所に保管・共有する運用が必要になります。私のオフィスではDropbox/Box/OneDrive/Googleドライブなどのクラウドストレージサービスを使い分けてますが、相手の環境も考慮する必要があるため強要はできません。結果として複数の環境を相手によって使い分けることになります。ツールやサービスの機能も一長一短なのでどれか一つに統一することもできず、このあたりの運用はまだまだ試行錯誤です。
紙で収集した資料もScanSnapでデータ化して一元管理することで、紙ファイルを取り回す手間が大幅に削減できます。こちらの運用はだいぶ定着して参りまして、オフィス内は必要最小限の紙資料しかありません。
- 期中データをしっかり整備してないと効率化にも限界あり
申告作業では基礎データとなる会計帳簿がきっちり作られていることが前提になるのですが、期中の作業は放置して帳簿作成から実質スタートとなると、どれだけツールやサービスを使って効率化を図ってもどうしても物理的に時間がかかる作業になります。こればかりは期中の帳簿作成作業をいかに平準化し、決算書作成や申告書作成にスムーズに移行できるかどうかがポイントになります。クライアントの協力は欠くことができません。
- 作業ログの記録が肝要
やりとりが煩雑になるクライアントの場合は作業メモに逐次記録を残すようにしました(テキストファイルなどシンプルな手段を使います)。結果、従前に比べて確認事項や資料の抜け漏れが少なくなりました。普段からbasecampでメールの過去ログは保存していて検索すればある程度情報は拾えるのですが、重要なやりとりとなると能動的に書き残す作業がより有効になります。スタッフへの引き継ぎにも役立ちそうなので、この方法は来年も継続していく予定です。
こんなところでしょうか。
なんだかんだとまた来年もどたばたしたシーズンになりそうです。
※当事務所へのお問い合わせはこちら。決算申告以外に、期中の経理作業効率化についてもお気軽にご連絡ください。

(画像は http://arthurandersenco.com/en/ より)
週刊「経営財務」No.3301の飯田信夫氏による「アーサーアンダーセン復活に立ちはだかるもの」というコラムがあったので、非常に興味深く読みました。
アーサーアンダーセン(アンダーセン、以下AA)は2002年に消滅した大手監査事務所の名称ですが、フランスのビジネスマンが26カ国で近くサービスを開始するとのこと。一方ですでに名称やロゴを利用している事務所があり、権利の主張合戦になっているようです。
Andersen Taxという名称で税務サービスをやっている事務所もあるようです。こちらはAAとは無関係。
http://economia.icaew.com/en/news/march-2017/legal-fight-over-iconic-anderson-name
そういえば私のLinkedInにも唐突にアナウンスがやってきました。
AAは自分が最初に働いた事務所で、IT業界に転身する1998年まで6年半ぐらい籍を置いておりました。外資系ファームであることや研修制度の充実に惹かれて入所したものの、その後の大手事務所の合併に飲み込まれていったという歴史があります。当時は「ビッグ8」と呼ばれる8大事務所でした。一定の年代以上の方には懐かしい事務所名が並びます。
- Arthur Andersen →消滅
- Coopers and Lybrand →PwC
- Ernst & Whinney →E&Y
- Deloitte Haskins & Sells →Deloitte
- Peat Marwick Mitchell →KPMG
- Price Waterhouse →PwC
- Touche Ross →Deloitte
- Arthur Young →E&Y
その後、合併統合を経て4大事務所(ビッグ4)に収斂していき、現在に至ります。
https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Four_accounting_firms
監査事務所「アーサーアンダーセン」とコンサルティング会社「アンダーセンコンサルティング(アクセンチュア)」の訴訟合戦というのも、すでに知る人が少ない過去のニュースですね。
AAは非常に優秀な同僚や先輩に恵まれた職場でした(研修マテリアルや監査調書は英語で参りましたが)。外国人比率や女性の比率も高くて理想的な職場環境ではあったのですが、合併統合のなかで外資系ファームの色が年を経るごとに薄まっていくさまを見るのはなんとも寂しいものがありました。
転職後数年してエンロン事件が起こり、AAは消滅することになりました。すでに別業界に居たので、どこか別世界の出来事のように記憶しています。超大手事務所でもかくも簡単に消滅することを実感したので、昨今の不祥事で名だたる大企業が上場廃止や消滅の憂き目に遭うことについては、ある意味耐性のようなものができたかもしれません。そういえば入所時にもらったAAのロゴ入りレポートパッドがものすごく使い勝手がよかったのにその後紛失してしまってとても残念。
個人的には、すでに終わったAAというブランドを奪い合うのがなんとも滑稽で今更感がありますが、利用できるものはほとぼりが冷めればなんでも利用する、という貪欲さがビジネスには必要なのかもしれません。
AAの成長と没落の帰結を書いた一冊がこちら。邦訳は出ていないようです。
Final Accounting: Ambition, Greed and the Fall of Arthur Andersen
※当事務所へのお問い合わせはこちら。お気軽にご連絡ください。
せっかくマイナンバーカードも作ってみたことなので、カードに埋め込まれている電子証明書について少し調べてみました。それにしても公的個人認証サービス広報用ロゴマーク「マイキーくん」ちっともかわいくないですね。(正直)

公的個人認証サービスによる電子証明書
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/kojinninshou-01.html
説明図表をクリックすると図が拡大「しない」点も不親切。読ませる気はあるのでしょうか。
マイナンバーカードについての自分の理解は
- カードの有効期限は発行から10年間
- 電子証明書の有効期限は発行日から5回目の誕生日まで
というなんとも適当なものですが、そのあたりもちゃんと書いてあります。電子証明書は
- 署名用電子証明書(e-Tax等の電子申請など、文書の真正性を証明する)
- 利用者証明用電子証明書(ログインした者が利用者本人であることを証明する)
の2種類が登録されており、それぞれに秘密鍵が設定されています。
公的個人認証を使ったオンライン手続についても記述があります。
- 目的の行政手続きや民間サービスのページを確認する
- パソコンなどの用意
- マイナンバーカードへの電子証明書の記録
- 公的個人認証を利用したオンライン手続
1から3まではマイナンバーカードを受け取ったときに完了してるので、利用者自身で行うのは4ということになります。
さて、マイナンバーカードに設定するパスワードは4種類あります。
- 個人番号カード(住民基本台帳用) 数字4桁
- 券面事項入力補助用 数字4桁
- 公的個人認証情報の利用者証明用 数字4桁
- 公的個人認証情報の署名用暗証番号 英数字6-16桁
数字4桁のほうは「利用者用」のもの、英数字16桁のほうは「署名用」のものと使い分けられてるのは理由がわかりましたが、利用者用がさらに3つに分かれている理由はわかりません。なんなのもう。
税理士の場合は「日本税理士会連合会」で発行している電子証明書カードがあり、e-Taxへの送信はこの情報を使っていまのところ不自由は感じておりません。マイナンバーカードで申告を行う日は訪れるのでありましょうか。
※当事務所へのお問い合わせはこちら。電子証明書に関するご不明点やそれ以外についてもお気軽にご連絡ください。
今日も元気だメールが重い。

Gmailで添付できるファイルのサイズが20MBから50MBまで拡大したらしいのですが
Gmail、受信可能な添付ファイル容量を50MBにアップ
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1703/02/news068.html
なんとも「これじゃない」感が漂います。Googleには添付ファイルの機能拡張ではなくて、添付ファイルを代替する機能を追求していただきたかった。(Googleドライブの利用を推奨してはいますね)
メールの添付ファイルは相手の環境に左右されず自由に送信することができるので多くの場面で利用されていますが、以下のデメリットがあります。
- 添付ファイルのデータが(能動的に削除しない限り)送信側と受信側双方のメールボックスに残る
- ファイルサイズが大きい添付ファイルはネットワーク帯域を圧迫する
- 受信側のファイルサイズ制限でうまく送信できないことがある(送信側にはエラーメールが届く)
私も業務上やむをえず添付ファイルを使うことが多く、こうしている今も受信したメールにいろんなファイルが添付されてきていて、削除しない限り残る気持ち悪さと日々向き合っております。送信時はパスワード付き圧縮ファイルを作成したり展開したりしつつ、この慣習はなんとかならないかなと。POP/SMTPプロトコルを使用したメールが確実に到達することが保証できないことは明白なのに、一度世の中に定着した慣習はよほどのきっかけがないと変化することはないようです。共通のファイルを複数者間で更新してるときのストレスは特に高く、添付ファイルの空中戦をしながら遠い目をしています。
ちなみに外資系企業でよく見る「パスワード付き圧縮ファイルとパスワードを別送信する」といった運用は、ネットワークを継続的に監視している限り意味をなさないし、パスワードをメール本文に平文で書いている時点で不合格。今や単なるおまじないのレベルでしょうか。
添付ファイルを代替できる機能としてはクラウドサービスのファイル/フォルダ共有機能があります。私の場合は
を相手によって使い分ける感じですが、これも受信側でアカウントがないとうまく共有できなかったりと使い勝手はいまひとつ。宅ふぁいる便のようなファイル転送サービスも、重要ファイルをやりとりするには抵抗があります。
- 受信側の設定が特に不要
- 高度なセキュリティが維持される
- 一定時間が経過すれば自動的に削除される
といった条件を満たすB2Bのサービスがあれば喜んで使うところなのですが。Boxは惜しいところまでいってますが、完璧とはいいがたい。
「FAX」「固定電話」「メール添付ファイル」は三大世の中から消滅してほしい慣習なのですが、ブレークスルーが起きてくれないものかと思います。
※当事務所へのお問い合わせはこちら。ファイル添付はできませんがお気軽にご連絡ください。
所得税確定申告の〆切が近づいてまいりました。

今年から年末調整や確定申告にもマイナンバー情報が必要になったため、マイナンバー情報の提出や収集のやりとりがすっかり風物詩となりました。マイナンバー情報の提出には
- マイナンバーカードの写し
- マイナンバー通知カードの写し+本人確認情報
のいずれかが必要になります。
納税をはじめとしてさまざまな行政手続に活用できるので、マイナンバーカードを作っておくのもそれなりにメリットがあると思い私もようやくマイナンバーカードを作りました。結論から書くととてもとても面倒でした。
マイナンバーカードの交付手続はこちらに書いてあります
https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/
通知カードが各世帯に届いているとして、具体的には以下の手順で進みます。
- カードを取りに行く日を決める(予約電話をする日から5営業日以上先)
- 専用受付番号に予約電話をして取りに行く日を確定する(その場で日付時刻のメモを求められます)
- 持参物を確認する(申請用紙、到着ハガキに署名捺印、通知カード、本人確認情報など。住基カードがあれば追加)
- 予約当日に現地に行く
- 申請書類一式と本人確認情報を提示する
- 4つの暗証番号をその場で決める(手元の書類に書くことを推奨されます)
- 端末で暗証番号を入力する(マイナンバーカードにデータが書き込まれます)
- 登録完了
写真つきマイナンバーカードを受け取るのに本人がそこにいてさらに写真付き本人確認情報を提示するとか、何かのコントかと思うやりとりでしたが担当者の方は真面目に作業に取り組んでますので文句も言えません。
暗証番号もなぜか4つも作らされます。
- 個人番号カード(住民基本台帳用) 数字4桁
- 券面事項入力補助用 数字4桁
- 公的個人認証情報の利用者証明用 数字4桁
- 公的個人認証情報の署名用暗証番号(e-Taxなどに使う暗証番号) 英数20桁大文字小文字区別せず
1.2.3.は同じ番号でもよいそうですが、なぜ最初から1つにしないのでしょうか。それに4桁の番号はともかく、長い英数文字列をその場で考えろというのも不親切です。(私もその場でPCを起動してパスワードジェネレーター使おうかとも思いましたが、面倒なので適当に考えたランダム文字列にしました)
また、カード表面には電子証明書の有効期限や臓器提供意思を自分で追記できるようになっているのですが、この文字が小さすぎて読めません。近くの文字が読めなくなる若者以外が罹患する謎の病(まわりくどい)がどんどん進行している私からすると、読ませないようにするためではないかと疑いたくなるような仕様。これも無理矢理盛り込んでいるとしか思えない。
とにかく早くマイナンバーカードを手元に届けようとか、利用者の利便性を考えようという考えは棚上げされて、ひたすら手続を煩雑にしてマイナンバーカードを作る気をなくそうという意図すら感じられるフローでした。このようなやり方では普及はまだまだ先になりそうで、制度そのものも中長期的に維持できるのかどうか疑問ですが今後どうなってしまうのでしょうか。
※当事務所へのお問い合わせはこちら。お気軽にご連絡ください。
https://ssl.form-mailer.jp/fms/e5d2273b248067
(余談)
ちなみに現地を後にして数分後に
「いまここに俺がこなかったか!?」
と銭形警部風に言ってみようかと頭をよぎったのですが、さすがに大人げないのでやめました。

本年度も確定申告シーズンが到来しました。所得税確定申告作業を電子的に行う、いわゆる「e-Tax」は以前に比べるとだいぶ普及してきた感があります。ここでe-Taxと呼ぶ場合、
- e-Taxウェブサイトにある「確定申告書作成コーナー」で確定申告書類を作成して書面で提出する
- e-Taxウェブサイトにある「確定申告書作成コーナー」で確定申告書類を作成して電子データで提出する
- 申告専用ソフトで確定申告書類を作成して電子データで提出する
といったさまざまな用途を指す言葉として広く使われているので、関係者の間でもときどき混乱があるようです。
さて、e-Taxでの申告書提出方法は大きく分けて3つあります。
書面提出の場合(本人または代理人が作成)
- 確定申告書類を作成する(ブラウザにて確定申告書作成コーナーの画面より入力)
- 完成したデータを印刷して提出書面にする
- 提出書面を郵送または窓口で提出する
電子送信の場合その1(本人が作成)
- 確定申告書類を作成する(ブラウザにて確定申告書作成コーナーの画面より入力)
- 完成したデータに電子的な署名を追加して送信する(カードリーダーや電子証明書が必要)
電子送信の場合その2(税理士など、代理人が作成)
- 確定申告書類を作成する(申告専用ソフトより入力)
- 完成したデータに電子的な署名を追加して送信する(カードリーダーや電子証明書が必要)
一般的に「申告は税理士に頼んで」というときは上記「その2」に該当します。電子証明書は住民基本台帳カードやマイナンバーカードなど、証明書情報がICチップに埋め込まれたものを使うケースが多いかと思われます。
書面提出は従来紙で行っていた作業の作成部分を画面に置き換えたシンプルなフローになります。この場合の画面UIや提出フローは非常にシンプルかつ親切に設計されていて、納税者自身の操作でも大きな混乱はなく申告完了までたどりつけるでしょう。税務署の確定申告書作成支援会場にはこれらの入力画面を使える端末がいくつか用意されているので、係員のガイドに従って操作すれば誰でも使えることでしょう。(混雑しますが)
一方、電子送信で申告書を送信しようとしたとたんに作業のハードルは一気にあがります。
上記その1(本人が提出する)の場合はこんなデメリットがあります。
- e-Taxで送信するためにカードリーダーや電子証明書を調達するコストがかかる
- 電子証明書による署名追加や送信の操作に慣れないため時間がかかる
上記その2(代理人が提出する)の場合はこれらに加えて
- 申告専用ソフトの操作性が非常に悪い
- 会計ソフトと申告ソフトの連動が中途半端で、二重入力が大量に発生する
- 結果、作成とチェックにいたずらに時間がかかる
という状況になります。多くの申告書を作成することで業務フローには慣れていても、特に申告ソフトの操作はいつまでたっても効率を上げることができず、私もストレスを感じながらこの時期を過ごしています。
申告ソフトは国が提供する純正「e-Taxソフト」や、市販では「達人」といったパッケージソフトなどがありますが、どれも一般利用者を想定していないせいか操作感が悪いという状況にあります。特に「e-Taxソフト」のUIは、必要な機能をとにかく詰め込んだだけで操作感をまったく考慮していないため、非常にストレスのたまります。国の肝いりで多額のコストをかけたのにこの完成度には大いに疑問を感じます。
「e-Taxソフト」が使いにくい原因としては以下が考えられます。
- 申告書の様式を画面で再現することを基本にしているため、操作性の向上に限界がある
- 仕様書どおりにとにかく機能を実装した結果、全体のバランスが崩れて改善ができない
- ソフトの利用者が企業や会計事務所なので、操作性を上げるモチベーションがそもそもない
長々と書きましたが、端的に言うと
e-Taxソフト使いにくすぎるのでなんとかしてくれ
という話でした。いやちがうな。これまでの歴史を踏まえてもうe-Taxソフトそのものがよくなることはほぼ諦めてるので、同じ機能をスムーズに実現してくれる破壊的プロダクトの出現を待望しているこの頃です。
※当事務所へのお問い合わせはこちら。お気軽にご連絡ください。

確定申告シーズン到来ですが、少々息切れ気味です。
時節柄か、新規のお客様の問い合わせも不定期でお受けしているのですが、開業まもないお客様の場合は多くの共通した悩みがあります。典型的には以下のような内容です。
- 開業資金はいくら用意すべきか
- 資本金はいくらにすべきか
- 開業届など届出書類はいつ出すべきか
- 銀行口座やクレジットカードは個人名義でよいのか、法人名義が必要か
- オフィス環境は整えるべきか、最初は自宅でよいか
- 事業資金を銀行から借入すべきか、できるのか
- 日々の取引をどのように記録していくのがよいか、領収書保管はどうするか
- 会計ソフトはなにを使うべきか
このような相談はお客様の置かれた状況によって解が異なるので、状況をお伺いして適切な回答になるよう都度考えることになります。今後はこのような相談も、いわゆるAIの発達によって定型化・自動化が図られていくのかもしれないな、とふと考えたりします。定型業務と違って多くの変数があるので簡単にはいかないと思いますが、そんな時代はまだ先と思っている間に記帳作業や仕訳登録はクラウド会計ソフトによって自動化されてしまいました。開業相談のような変数を限定できそうな個別の相談業務もいずれはそうなるという前提で、AIを活用しつつ独自の付加価値を提供していく方法を考えていくことが避けられなさそうです。
※当事務所へのお問い合わせはこちら。お気軽にご連絡ください。

本年度の法定調書業務もなにごともなく無事完了しました…と言いたいところですが、今年は少々事情が違ったようで、地方税ポータルシステム(eLTAX)でトラブル続きで参りました。提出期限の1月31日前後にeLTAXのシステムへのアクセスが集中してつながりにくいという状況が続き、現在も収束しておりません。
私自身の業務としても26日前後はまだましでしたが、27日から31日まではほとんどつながらなかったという印象です。あまりにトラブルが続くので、eLTAX自身や自治体も2月1日までの受理を容認するという声明を出さざるを得ない事態になっています。
eLTAX(地方税ポータルシステム)
eLTAX へのアクセス集中に伴う、法人事業税、地方法人特別税、法人都民税、事業所税、固定資産税(償却資産)の申告書の対応について(東京都主税局)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/oshirase/2017/20170131.pdf
eLTAXにアクセスできない。遅延?寝てるの?税理士の悲鳴続出(togetterまとめ)
https://togetter.com/li/1076027
1月末は「合計表」「給与支払報告書」「償却資産税申告書」と提出期限が集中する時期なので(11月決算法人の申告期限でもあります)、このような状況は容易に予測可能かと思われます。今年のような状態は来年は万全に対策してもらいたいものです。
さて、本題はここからになります。毎年この時期に行われる法定調書業務をざっくり表現するならば
「昨年一年間の給与や報酬の支払い状況をとりまとめて税務署や自治体に対して報告する」
という仕事で、よりぶっちゃけて書くならば
「徴税業務の代行作業(税務署や自治体の作業負担が企業や会計事務所に転嫁される)」
といえます。業務として手掛けておきながら書くのも気が引けますが、体よく当局の作業の肩代わりを押し付ける制度設計になっている感は否めません。そのわりには法定調書業務は煩雑な手順を踏むのですが、具体的には次の手順で進められます。
- 毎月の給与・報酬について支払金額・源泉所得税の金額を集計する(給与計算ソフトなど)
- 所定の書式に集計金額を転記する(申告ソフトなど)
- 作成した書式を出力して金額をチェックする
- e-TaxやeLTAXのシステムから電磁的に書式データを提出する
思いつくだけで「給与計算ソフトへのデータ入力」「給与計算結果の目視チェック」「給与計算ソフトから申告ソフトへの転記」「申告ソフトから出力した提出書面データの目視チェック」「申告システムへの提出」という場面でそれぞれ手作業が発生しており、目視チェックは仕方ないにしても非常に効率の悪い作業に思えます。
一定人数以上の企業であれば源泉所得税の集計と支払いは毎月行っているはずですので、従業員ごとの支払額や源泉税額をマイナンバーで名寄せして当局側で集計することもできるはずなのに、そのような制度設計にはなっていません。当局にしてみればおそらく既存の書式を変更ないし廃止するインセンティブは働かないので、書式どおりに提出されることが優先なのでしょう。これはマイナンバーが導入されても大きな変化はなく、むしろより煩雑になった感があります。
しかしよくよく考えてみると法定調書のとりまとめに必要な要件はそれほど多くありません。代表的な書面についていえば、必要なデータは以下のとおりです。
- 給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書(個人別明細書)※確定申告向け情報を除く
- 受給者の住所・氏名・個人番号
- 受給者の支払金額・社会保険料等の金額・源泉徴収税額
- 報酬等の支払調書
- 受給者の住所・氏名・個人番号
- 受給者の支払金額・源泉徴収税額
- 法定調書合計表
- 給与・報酬の人員・支払金額・源泉徴収税額(うち、当局への提出対象は何人か)
- 不動産使用料その他についての人員・支払金額
- 給与等の支払状況内訳書
- 給与の支給総額・算出税額・支給月日・納付月日
- 報酬の人員・支払総額・税額・納付月日・号区分ごとの内訳
- 給与は役員向けか従業員向けか
企業側からすると、期中の給与や報酬に次のような情報が含まれていればこれらの自動集計も容易に実現できることがわかります。
- 受給者の住所・氏名・個人番号
- 受給者が役員か従業員か
- 報酬の場合はどの号区分に該当するか
- 支払金額が源泉税対象の支払かどうか
せっかくマイナンバーがあるので、やろうと思えば支払先ごとの名寄せもできるはずですし、法定調書の書式に落とし込む作業も当局側で行って事業者側は確認すればOK、という運用もできるはず。たとえばこんな感じで。
- 毎月の給与・報酬について支払金額・源泉所得税の金額を提出する
- 当局側でマイナンバーごとの名寄せと金額集計が行われる
- 法定調書データへの落とし込みやドラフトの確認まで当局側で行い、年明けにデータが送られてくる
- 企業側で確認したら、そのまま提出完了
そのようにはならずに現行制度で法定調書(画面や紙)にわざわざこれらのデータを再入力して改めて書面で提出するという状態になっている現行の制度設計は、非常に効率が悪いと思いますがいかがでしょうか。eLTAXの使い勝手以前に、提出業務そのものにメスを入れる必要があるように思えます。
この時期に多くの企業や会計事務所が法定調書の作成に追われることそれ自体に漠然と(というか露骨に)疑問を感じてしまったのでやや極論を書いてみましたが、法定調書業務に今後イノベーションは起きるのでしょうか。直接的にメリットを受けるのは企業そのものより会計事務所という一部のマーケットという気もしますが、この領域でのバックオフィスの非効率を解消する動きに淡い期待を持ちつつ、来年の法定調書業務も頑張りたいと思います。
※当事務所へのお問い合わせはこちら。お気軽にご連絡ください。

前のエントリではさらっとマイナポータルについて書いてしまいましたが、サービスがリリースされて以来いろいろ問題視されているようです。
「マイナポータル」の動作環境が絶望的と話題
https://r25.jp/society/00055146/
内閣府のマイナンバーポータルサイトにバグがあるとの情報 201701202131
https://togetter.com/li/1072479
問題の所在はいくつかありますが、大きく以下の点に集約されるようです。
- 利用者はICカードリーダーの手配が必要なため初期コストがかさむ(これは電子証明書を利用するサービス共通の問題)
- 推奨環境が限定されていてユーザーに必要以上に負担を強いる
- 推奨環境自体に脆弱性がありセキュリティリスクをユーザーに転嫁している(そもそもJavaアプレットやActiveXコントロールの利用を強要しているのは筋が悪い)
個人的に1.は仕方ない面があるものの、2.3.についてはサイト運営者の努力で解決できるレベルかと思われます。安心して使える環境が整うまでは静観しているのが安全かもしれません。
という私もマイナンバーカードを作ってみたものの利用する機会が「乞われたときにマイナンバーを提供するとき」ぐらいしかなくて費用対効果はいまいちです。行政手続に限定して利用されるマイナンバーですが、現段階でこの状態ではあまり活用する機会が拡大することもなさそうです。
※当事務所へのお問い合わせはこちら。お気軽にご連絡ください。
法定調書・申告シーズン真っ盛りです。
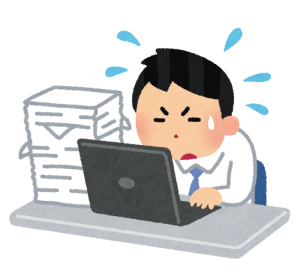
さて、マイナンバーのポータルサイト(マイナポータル)と国税電子申告・納税システム(e-Tax)が連携したというニュースが流れてきました。
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_290113_mynaportal.htm
具体的には
- マイナポータルにe-Taxの認証情報(利用者識別番号とパスワード)を設定する(初回のみ)
- マイナポータルにログイン後、e-Taxにログインすることなく国税の申告・申請手続ができる
ということのようです。実際に試したわけではないのでなんともいえないですが、現段階で利用できる手続は以下のとおりです。
- 納税関係
- 納税証明書関係
- 源泉所得税関係
- 法定調書関係
- 添付書類関係
マイナポータルを利用するのは基本的に個人でしょうから、現段階では納税証明書の発行申請がマイナポータルから利用できるようになるという点で便利になります。
そして大変残念なことに、個人でもっとも利用されるであろう所得税の確定申告はこの連携の対象外らしく、以下の文言が出てきます。
所得税の申告書等を作成される方は、確定申告書等作成コーナーをご利用ください。同コーナーを利用して作成した申告書をe-Taxにより提出される場合、上記のマイナポータルを経由してログインした場合でも、送信の際には、従来どおりe-Tax用の利用者識別番号と暗証番号を入力する必要がありますのでご留意ください。
マイナポータルもいろいろがんばっているようですが、もっとも高いであろう需要に対応していないのはいただけません。
今後の対応を期待したいと思います。
