
原幹公認会計士事務所
エンジニア・クリエイターのための会計事務所です。会計やICTに関連したトピックを書いてます【新型コロナ対策】東京都感染拡大防止協力金の申込がスタートしました
水曜日 , 22, 4月 2020 未分類 【新型コロナ対策】東京都感染拡大防止協力金の申込がスタートしました はコメントを受け付けていません
東京都感染拡大防止協力金の申込が4月22日からスタートしました。1事業所は50万円、2事業所は100万円まで支給されますので、短期的に資金繰りが厳しい事業主の方向けの制度なので、積極的にご利用検討ください。
東京都感染拡大防止協力金のご案内
https://www.tokyo-kyugyo.com/
新型コロナウイルス感染等拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、
https://www.tokyo-kyugyo.com/
施設の使用停止等に全面的に協力いただける中小の事業者の皆様に対し、
協力金を支給いたします。
なお、申請にあたっては会計士・税理士など専門家の確認が推奨されています。
円滑な申請と支給に向けて、専門家の確認を受けていただくようお願いします。事前確認を行う専門家は以下のとおりです。
https://www.tokyo-kyugyo.com/
東京都内の青色申告会
税理士
公認会計士
中小企業診断士
※これまでにアドバイスや指導を受けている上記に該当する専門家がいる場合は、その方へ事前確認を依頼してください。
※専門家に依頼した事前確認にかかる費用については、一定の基準により東京都が別に措置いたしますので、そのことを前提に専門家とご協議ください。
新型コロナウィルス対策(Googleスプレッドシート)※更新中
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MFZuPfrbkr–HOYlnJfW4YFlVYkOHEd1YkTPKXamEZs/edit#gid=0
当事務所でも各種ご相談を承ります。お問い合わせはこちらへ
「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の更新
火曜日 , 14, 4月 2020 未分類 「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の更新 はコメントを受け付けていません
新型コロナウィルス対策について、国税庁FAQが継続更新されていますのでご紹介します。
「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の更新(令和2年4月13日)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
更新内容は以下のとおりです。
6 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
<法人税に関する取扱い>
問1.企業が生活困窮者等に自社製品等を提供した場合の取扱い
問2.法人税の災害損失欠損金の範囲について
問3.企業がマスクを取引先等に無償提供した場合の取扱い
問4.賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合
問5.企業が復旧支援のためチケットの払い戻しを辞退した場合
問6.業績が悪化した場合に行う役員給与の減額
問7.業績の悪化が見込まれるために行う役員給与の減額
<所得税に関する取扱い>
問8.個人事業者の事業所得に赤字(損失)が生じた場合の取扱い
問9.個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い
問10.青色申告の承認申請の取扱い
新型コロナウィルス対策(Googleスプレッドシート)随時更新中
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MFZuPfrbkr–HOYlnJfW4YFlVYkOHEd1YkTPKXamEZs/edit#gid=0
当事務所でも各種ご相談を承ります。お問い合わせはこちらへ

在宅勤務に最適なのは3スクリーンという興味深い記事でした。
iPadを活用した3スクリーン在宅勤務
https://note.com/takujihashizume/n/n388c56816084
特にコミュニケーション用と作業用のスクリーンを分離することで集中力を保つという工夫が参考になります。
その他も学ぶ点が多いエントリですが、省みて自分の環境を見るとだいたい以下のような状態になっています。(自分の場合はWindowsメインなのでちょっと変わりますが)
- スクリーン1 Windows Desktop 成果物作成用(1)+モニタ1枚
- Google Chrome/Box/G Suite/Microsoft Office
- スクリーン2 Windows Desktop 成果物作成用(2)+モニタ1枚
- 1と同じ+税務申告ソフト(弥生、達人など)
- スクリーン3 Windows Notebook コミュニケーション用
- メール/Slack/Teams/Chatwork/Trello
- スクリーン4 iPad Pro 9.7インチ 対面・肉声打ち合わせ用
- Hangouts meet/Zoom/Skype
- スクリーン5 MacBook Pro 15インチ
- おまけ。プライベートで音楽と動画とSNS垂れ流し
スクリーン1はモニタ2枚構成でしたが諸事情あって現在は1枚に。スクリーン2はスクリーン1とほぼ同じ構成ですが、少し重めのDBMSを常時使うので別環境にしています。
外出時はスクリーン1の役割をスクリーン3(ノートブック)が負うことになり、成果物作成+コミュニケーション用になります。ただし生産性は著しく下がるのであくまで手短に社外でコミュニケーションをとるときのみ。時間や場所がないときはスマホで対応します。
このように環境を分けているつもりですが実際はこれほど綺麗には分離できてなくて、スクリーン1と3と4が微妙に混在しています(スクリーン1でコミュニケーションをとってしまうことが多い)。コミュニケーションによる割り込みを防止するに3や4を別環境に分けるというのは大事なポイントかと思います。気が散りやすいので、通知が来るとどうしてもそちらに関心が行ってしまうのはオンラインミーティングの比率も高まる一方だし、これから集中的に原稿書きに時間をとる状態に入るため、スクリーン1に集中する時間をいかに確保していくかが課題になりそうです。
4枚は多すぎると思いますが、ひとまずコミュニケーション用と作業用でスクリーンを分けるのはすぐにでも手がつけられるので、ぜひお試しください。
(余談)ちなみに上記の環境に加えてモバイル端末があるので(携帯2台にモバイルルーター1台)で合計7枚の液晶に常時取り囲まれていることになります。私は一体何をしてるのでしょうか。

新型コロナウィルス対策の情報が各所に散逸しているので、もっぱら備忘を目的としてGoogleスプレッドシートで一覧化しました。
新型コロナウィルス対策(Googleスプレッドシート)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MFZuPfrbkr–HOYlnJfW4YFlVYkOHEd1YkTPKXamEZs/edit#gid=0
内容順次追加予定です。 どなたでもコメントできますので、追加情報や改善のご意見などをお送りいただければ幸いです。
2020.05.02追記
特別定額給付金(一律10万円給付) を追加
2020.04.23追記
業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)事業 を追加
2020.04.13追記
経済産業省 中小・小規模事業者等を対象に資金繰り支援及び持続化給付金 直通番号を変更
新型コロナウイルス感染症特別貸付(国民生活事業・中小企業事業)を追加
2020.04.09追記
国税庁 在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ(期限付酒類小売業免許の付与について)を追加
2020.04.08追記
中小・小規模事業者等を対象に資金繰り支援及び持続化給付金に関する相談 を追加
開示関連の対策を追加
東証 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた対応方針について
法務省 定時株主総会の開催について
金融庁 新型コロナウイルス感染症の影響による金融機関等の報告の提出期限について
2020.04.07追記
助成金 に 新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例的なコース を追加
生活福祉資金貸付制度及び特例を追加
2020.04.05追記
参考 に 新型コロナウイルス 支援情報まとめ Money Forward を追加
新型コロナウイルス感染症:拡大防止活動基金 を追加
猶予・延長 に申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の柔軟な取扱い を追加
2020.04.04追記
問い合わせ先電話番号や検索URLを追加
当事務所でも各種ご相談を承ります。お問い合わせはこちらへ

新型コロナウィルスへの対応は依然として予断を許さない状況が続いています。この状況に鑑み、助成金・税務上の対応について以下サイトでまとめられていますので以下ご紹介します。
経済産業省
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#00
新型コロナ対応ポータルとしてあらゆる情報がまとまっています。こまめにチェックしてみましょう。
- 概略
- 信用保証
- セーフティネット保証4号・5号
- 一般保証と別枠で保証
- 4号は都道府県対象に100%保証
- 5号は影響を受けている業種に80%保証
- 危機関連保証
- セーフティネット保証と別枠で全国・全業種を対象に100%保証
- セーフティネット保証4号・5号
- 融資
- 新型コロナウィルス感染症特別貸付危機対応融資
- 売上高5%以上減少の事業者に対して当初金利0.9%引き下げ
- 特別利子補給制度
- 特別貸付を利用した事業者への利子補給
- 個人事業主は要件なし
- 小規模法人は売上高15%減少
- 中小企業は売上高20%減少
- 特別貸付を利用した事業者への利子補給
- マル経融資
- 小規模事業者は別枠で最大1000万円まで
- 金利を0.9%引き下げ
- セーフティネット貸付
- 基準金利での貸付(売上高等の要件なし)
- 新型コロナウィルス感染症特別貸付危機対応融資
- 信用保証
国税庁
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm
- 概略
- 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を令和2年4月16日(木)まで延長
- 国税を一時的に納付できない納税者に向けて、申請することで納税を猶予する制度の新設
- 原則として一年間の猶予
- 猶予期間中の延滞税の減免
- 財産の差押えや換価の猶予
(3/30 18:00追記)
厚生労働省 働く方と経営者の皆さまへ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#hatarakukata
- 概略
- 雇用調整助成金の特例措置
- 全国
- 1 雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者を助成対象とします(新規学卒採用者等、雇用保険被保険者として継続して雇用されている期間が6か月未満の労働者についても助成対象とします)
- 2 過去に受給していた事業主に対する受給制限の廃止について
- 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、以下のとおりの取扱いとします。
- (1) 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とします。
- (2) 通常、支給限度日数は1年間で100日、3年間で通算150日までのところ、今回の特例の対象となった休業等については、その制限とは別枠で受給可能とします。
- 追加の特例措置(緊急特定地域)
- 以下の厚生労働大臣が指定する地域及び期間においては、前記の特例に加え、次のとおり措置を講じることとします。
- ※厚生労働大臣が指定する地域:北海道
- 厚生労働大臣が指定する期間:令和2年2月28日から令和2年4月2日
- 1 雇用保険の被保険者以外の方も助成対象にします。
- 現行、雇用調整助成金は、雇用保険被保険者を助成対象としていますが、上記期間内における上記地域の事業者が休業等を実施した場合、1週間の所定労働時間が20時間に満たない労働者も助成対象に含めます。
- 2 休業を実施した場合の助成率を引き上げます
- 上記期間内における上記地域の事業所が休業を実施した場合の助成率を、中小企業の場合は2/3から4/5へ、大企業の場合は1/2から2/3へ引き上げます。
- 3 生産指標要件を満たしたものとして扱います
- 現行、販売量、売上高等の事業活動を示す生産指標の最近1か月間の月平均値が、前年同期と比べ10%以上減少している事業主であることを必要としていますが、上記期間内における上記地域の事業者が休業等を実施した場合、生産指標要件を満たしたものとして扱います。
- 以下の厚生労働大臣が指定する地域及び期間においては、前記の特例に加え、次のとおり措置を講じることとします。
- 全国
助成金の対応等をご検討される場合はお早めに窓口へご相談ください。事業者の皆様が一日も早く元の環境に復帰できることを祈念しております。
当事務所でも各種ご相談を承ります(状況に鑑み、ご相談はオンラインミーティングを前提とさせていただきます) 。お問い合わせはこちらへ
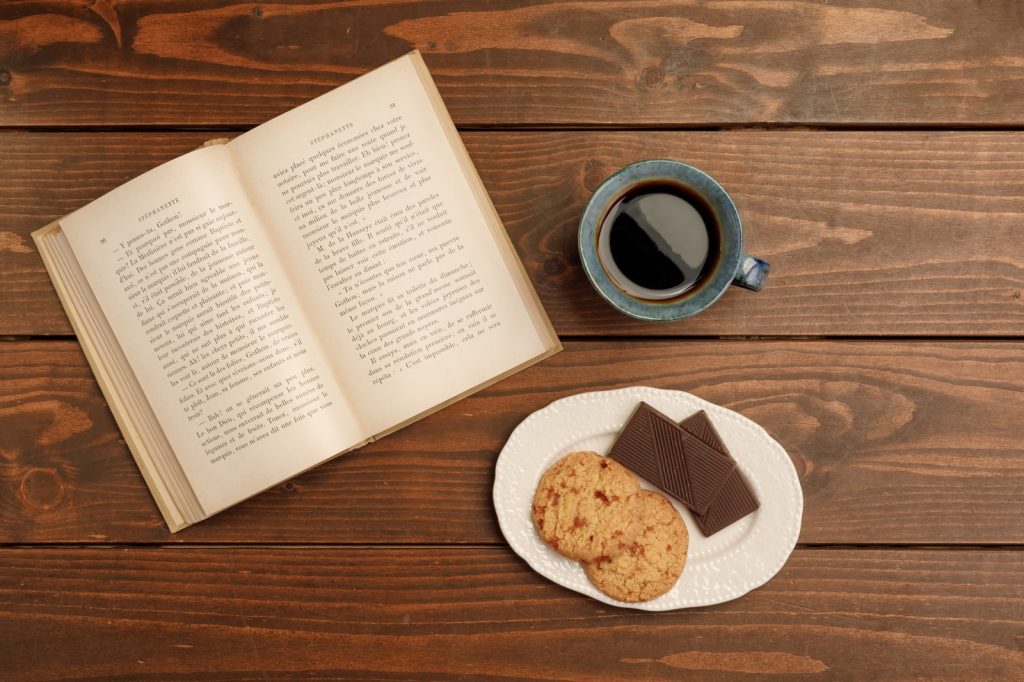

「海外資産投資と国際税務」。サブタイトルは「富裕層が知っておくべき」。個人的にも懇意にさせていただいている永峰潤・三島浩光両先生の共著になります。
(略)こうしたグローバルスタンダードともいえる資産運用を実践するに当たっても、今の時代は信頼できる専門家とタッグを組むのが良作となっているのです。そこで、その一助としていただくために、これまで私達が培ってきた知見の一部をわかりやすく紹介するために本書を執筆いたしました。
このような前書きで始まる本書は、主として富裕層を対象とした資産防衛の考え方について解説しています。
序章 近年、増え続ける海外への資産移転と税制の関係
第1章 海外資産を取得する際に知っておきたいポイント
第2章 海外資産を保有中に知っておきたいポイント
第3章 海外資産を処分する際に知っておきたいポイント
第4章 海外資産を相続する際に知っておきたいポイント
第5章 アメリカの税制概要
第6章 ハワイ、シンガポール、スイスの資産基礎知識
このような目次で、実務経験に裏打ちされた記述が多く、楽しく読み進められます。
日本国内に関していえば、国財財産調書の作成にはじまり資産の取得・保有・処分・相続という場面に際してさまざまな規制の網がかけられつつあり、今後その流れは全世界的に不可逆なものであることが理解できます。特に処分については方法を間違えると本来負う必要のないデメリットが生まれてしまう可能性もありさまざまな前提知識が必要になります。(詳細は本書にて)
本書を概観して思うのは、まとまった資産を保有する(もしくは保有しつつある)層にとっては今年来年といった短いスパンでなく5-10年単位で財産をどう管理するべきか(したいのか)といった長期方針が必要になっていくであろうこと、究極的には「自分の人生に財産をどう生かしていくのか」という羅針盤が必要になっていく時代なのではないかという点です。自分自身も富裕層のお客様と仕事で関わることが多いですが、小手先の節税術ではなく財産をどう守りそして生かしていくのかお客様と一緒に向き合うための動機付けになる、そんな一冊でした。
当事務所へのお問い合わせはこちら
【セミナー】 AIを活用し経理業務を「データサイエンス業務」に変革するためのポイントと実務 2020/04/02
火曜日 , 28, 1月 2020 未分類 【セミナー】 AIを活用し経理業務を「データサイエンス業務」に変革するためのポイントと実務 2020/04/02 はコメントを受け付けていません
前回好評につき、経理業務におけるAIやデータ分析の活用について登壇機会を頂戴しました。2月18日開催の「経理業務におけるテレワーク導入の実際」と併せ、ご興味持っていただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。
開催概要:
一般社団法人 企業研究会セミナー
タイトル:
AIを活用し経理業務を「データサイエンス業務」に変革するためのポイントと実務
~経理人材が今後目指すべき方向性を提示~
日時:
2020年04月02日 木 13:30~16:30
URL:
https://form.bri.or.jp/public/seminar/view/2146
※当事務所へのお問い合わせはこちら
https://ssl.form-mailer.jp/fms/e5d2273b248067
新年明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

2019年はラグビーワールドカップ2019日本大会が国内各地で開催され、大変な盛り上がりを見せました。個人的にはRWC観戦にひきずられて本業がおろそかになりがちなところをなんとか恙なく終わることができ、また社外役員として関与しているフリー株式会社が株式公開を果たすなど、大きな転換を迎える一年でもありました。
2020年も、さらに混沌としたビジネス環境の中で企業の大小を問わずすべての業種・業態で引き続き激しい競争に晒されていくと思われます。時代が変革していく流れを確実にフォローして、お客様の事業価値を更に高めていくための戦略パートナーとしてサービスをご提供できるよう、メンバー一丸となって今年も邁進して参ります。何卒よろしくお願い申し上げます。
クインテット・マネジメント・パートナーズ 原幹公認会計士事務所
代表 公認会計士・税理士・公認情報システム監査人(CISA)
原 幹
お問い合わせはこちらまで
2020年(令和02年)12月までの税務カレンダー(Googleカレンダー形式)を更新しましたのでお知らせします。

PC/スマホ/タブレット等でご利用ください。更新内容は以下のとおりです。
- 2020年1月-12月の項目を追加
基本的に毎年同じイベントですが、休日による変動が少し入るのでそのあたりを調整しています。
表示イメージは以下のとおりです。項目をクリックすると詳細が表示されます。カレンダー右下の「+」ボタンを押して、ご自分のカレンダーに追加することもできます。ご利用は自己責任にてお願いいたします。
(Google Chromeを推奨。環境によっては見えないことがあります)
以上、本年最後の投稿になります。
2019年もお世話になりました。来年も良い一年でありますように。
当事務所へのお問い合わせはこちらまで。カレンダーへのご要望もお待ちしております。
【会計人コース】『対談 税理士の役割は新たなステージへ-AI時代に勝ち残るための知識とスキル』が掲載されました
月曜日 , 16, 12月 2019 未分類 【会計人コース】『対談 税理士の役割は新たなステージへ-AI時代に勝ち残るための知識とスキル』が掲載されました はコメントを受け付けていません
「会計人コース」2020年1月臨時増刊号「税理士試験 みんなの合格体験記」に
特別企画1
対談 税理士の役割は新たなステージへ
―AI時代に勝ち残るための知識とスキル
freee株式会社CEO 佐々木大輔 × 公認会計士・税理士 原 幹
と題した対談を掲載いただきました。
AIが今後普及されると予想されるなか、会計人として生き残るために何をすべきか、対談を通じてお伝えできればと思います。ご一読いただければ幸甚です。
freeeの佐々木さんとは普段あまりしない話をしたので、個人的に新鮮な内容の対談になりました。
公式サイト
本記事へのご意見・ご感想はこちらへ
https://ssl.form-mailer.jp/fms/e5d2273b248067