
原幹公認会計士事務所
エンジニア・クリエイターのための会計事務所です。会計やICTに関連したトピックを書いてます2024年(令和06年)12月までの税務カレンダー(Googleカレンダー形式)を更新しましたのでお知らせします。

PC/スマホ/タブレット等でご利用ください。更新内容は以下のとおりです。
- 2024年1月-12月の項目を追加
基本的に毎年同じイベントですが、休日による変動を調整しています。
表示イメージは以下のとおりです。項目をクリックすると詳細が表示されます。カレンダー右下の「+」ボタンを押して、ご自分のカレンダーに追加することもできます。ご利用は自己責任にてお願いいたします。
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=harakancpa.com_2qhjtrecvq75rb5rjed2nlfnfo%40group.calendar.google.com&ctz=Asia%2FTokyoカレンダーのURLはこちらです。Google Chromeを推奨しますが、環境によっては見えないことがあります。うまく表示できない場合はブラウザでコピー&ペーストしてください。
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=harakancpa.com_2qhjtrecvq75rb5rjed2nlfnfo%40group.calendar.google.com&ctz=Asia%2FTokyo2023年はインボイス制度の適用に伴い混乱の年末を迎える展開になりました。依然として政情不安や為替の不安定など混沌とした一年だったと感じます。
2024年は改正電子帳簿保存法の本格適用やインボイス制度による初年度の税務申告を迎えます。企業側でそれらの対応に追われる日々は続くものと予想されます。
経理・財務・税務領域のデジタル化やAIの進化を受け、私たちの仕事も変革を迎えます。クライアントのニーズを適切に満たすことができるよう私たちも日々研鑽し、本業にフォーカスするクライアントのみなさまをこれまで以上に引き続きご支援して参ります。
以上、本年最後の投稿になります。
2023年も大変お世話になりました。来年もみなさまにとって良い一年でありますように。
当事務所へのお問い合わせはこちらまで。カレンダーへのご要望もお待ちしております。
丸善リサーチがなかなかいけてます。
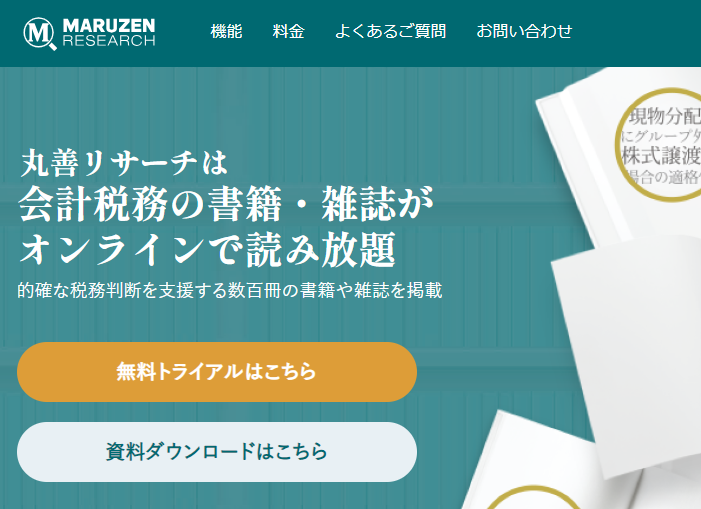
丸善リサーチとは
「会計税務の書籍・雑誌がオンラインで読み放題、的確な税務判断を支援する数百冊の書籍や雑誌を掲載」とのことで、会計・税務領域の横断検索サービスです。同業者の間でも評判が良いですね。
https://tax.maruzen-research.jp/
書籍については最新刊まではカバーしていないものの、近刊のカバレッジがなかなか高く、弊事務所で買い置きした積ん読専門書たちが早々にカバーされておりました。
こんなことができた
ざっくりこんなことができます。
キーワード「税務調査」→「書籍」「目次」で132件ヒット。最新刊行は2022年9月
キーワード「組織再編」→「書籍」「本文」で124件ヒット。最新刊行は2023年9月
キーワード「ベンチャー」→「書籍」「本文」で6件ヒット。最新刊行は2023年1月
「読む」→本文のページを開く
「書籍内検索」→関連キーワードをハイライトしつつ開く
「プレビュー」→検索結果を表示しつつ書籍内検索結果を開く(一番便利)
リサーチのアプローチが変化した
さて、このように便利なサービスが出てくるとリサーチのアプローチも自ずと変化していくことになります。たとえば、最近まではもっぱらこんな方法でした。
ネットでキーワード検索
→書籍を検索
→購入
そのうちこんな感じになりました。
ChatGPTで当たりをつける
→書籍を検索
→購入
今はこんな感じでリサーチしております。
ChatGPTで当たりをつける
→丸善リサーチで横断検索
→該当書籍で解答が得られれば終了、得られなければ近刊書籍を検索
→購入
よくよく考えてみれば、リサーチはなんらかの「解答」を求めて行う動作なので、ほしい情報に到達できれば書籍の体裁をとるかどうかは重要ではなかったりします。とはいえそれでは書籍の著者が発刊するモチベーションが低くなってしまうので、新刊の存在価値が低下することは当面はなさそうです。
というわけで、無料モニタリングの期間も終了し、12月から丸善リサーチが有料化(3,500円/月 消費税別)されるそうなので、より活用していきたいと思います。いまのところ会計・税務領域が中心ですが、専門領域への今後の拡がりが期待できそうです。
まあ、結局専門書は相変わらずどかどか購入しているわけですが。
[書籍]「チェックリストでリスクが見える内部統制構築ガイド」
日曜日 , 19, 11月 2023 未分類 [書籍]「チェックリストでリスクが見える内部統制構築ガイド」 はコメントを受け付けていません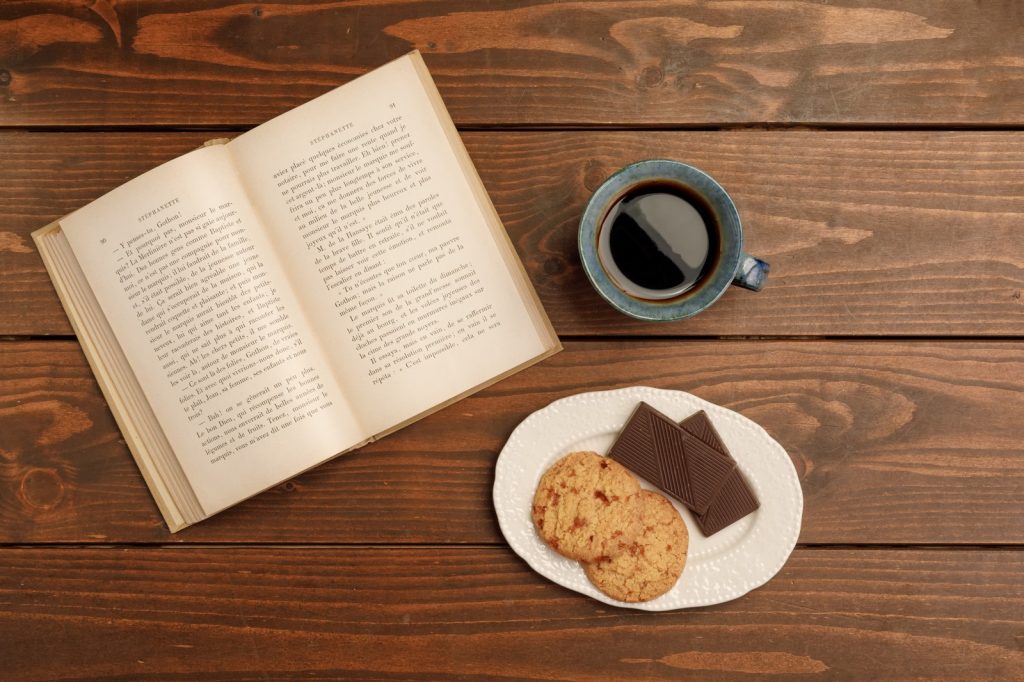
話題の新刊なので早速手を伸ばしてみました。

(オビより)
項目別のチェックリストを使って、個別かつ網羅的にリスクと対策を解説。監査法人・大手総合商社で培ったノウハウをまとめた1冊。改正内部統制基準等もフォロー。
2023年4月の内部統制実施基準の改正を踏まえ、実務視点での内部統制構築方法について書かれています。豊富なチェックリストと合わせ、Excelファイルのチェックリストをダウンロード可能です。(サンプル版は無料で完全版は有料)
JSOXの最新動向をコンパクトに把握しつつ、実務的なリストを利用したい読者向けには有用な一冊といえます。
第I部 内部統制の構築・運用に向けた基礎知識
「内部統制はなぜ必要か」「内部統制の構築に向けた基礎知識」など、基本的な知識確認のためのパート。基本知識があれば改正点をかいつまんで押さえれば十分だと思われます。
第II部 項目別チェックリスト
本書のメインパート。実務上リスクが高いとされる主要な内部統制項目ごとに「主要なリスク」「対策」「サンプル帳票」が紹介されています。本書で言及される項目は以下のとおりです。職掌柄IT統制のパートを時間をかけて読んでしまいますが、必要最小限のレベルは網羅しているように読めました。
- 全般的管理
- 現預金管理
- 小切手管理
- 売上債権管理
- 仕入債務管理
- 棚卸資産管理
- 固定資産管理
- 有価証券管理
- 経費管理
- 契約管理
- IT統制
- その他の内部統制
本書の読後感は以下のとおりでした。どうしてもIT統制がらみは辛口になってしまいます。これから内部統制評価を始めるときにリスクを特定する段階で迷っている読者には向いていると思いました。
よかった点
- IT統制の改正にも踏み込んで、比較的歴史の浅いトピックにも触れている(パスワードの定期変更やパスワード長など)
- Excelファイルのチェックリストが充実。本書の記載内容をほぼすべてカバーしている
- チェックリストが日英表記のため、海外グループ会社対応にも役立ちそう
残念だった点
- 文章で一気に説明するため読みにくいところがある、略称の説明が唐突に使われる(前半に顕著だった)
- 帳票の紹介が書面を基本にしたものがほとんどで、ワークフローを前提とした記述が全体的に少ない
- SaaS以外のクラウドサービスについてほとんど言及がない(財務報告目的と割り切ればこれはこれでありか)
- 電子署名やシステム承認を前提としたフローや統制についての記述がほとんどない(これは入れてほしかった)
- 統制項目ごとの評価プロセスや評価方法には触れていない(類書が多いのでそこは不要と割り切ったのかも)
当事務所のサービスメニューはこちらです
[書籍]「Pythonではじめる 会計データサイエンス」データサイエンス視点とテクニックを身に着けたい会計人必読の書
土曜日 , 27, 5月 2023 未分類 [書籍]「Pythonではじめる 会計データサイエンス」データサイエンス視点とテクニックを身に着けたい会計人必読の書 はコメントを受け付けていません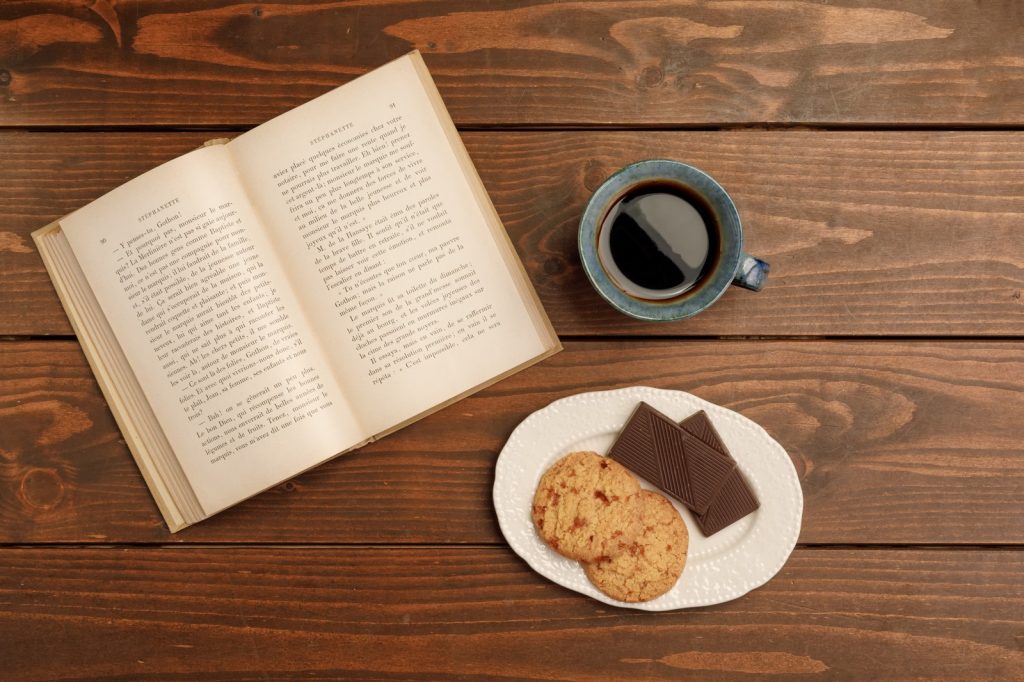
会計データサイエンティストを目指す方の必読書が出ました。

雑誌『企業会計』連載時にも興味深く読んでいましたが、今回書籍になることでまとめて読めるのはありがたいです。書籍になると読後感がまた違いました。
本書は冒頭で対象読者ペルソナが明記されてるので、ご自身が向いている読者層かあらかじめ確認する目安になるでしょう。個人的には「中規模から大規模組織の経理部門所属」がターゲットに思えました。サンプルコードもついている親切設計なので、実際に手を動かしてみるのが肝要です。
以下、各章について読後の感想です。
第1部『会計データサイエンスの基礎知識』では、初学者向けにデータサイエンスの基礎知識を解説しています。
第1章 会計データサイエンスの準備体操
第2章 Python入門
では、データサイエンス初学者向けにPythonやNumPyの基礎解説があり、予備知識のない読者でもは入りやすくなっています。Google Colaboratoryのインストールから解説しているのはわかりやすいですね。NumPyやpandasの機能解説については既知の読者は読み飛ばしてよいですが、おさらいに読むのがよいでしょう。
第3章 数学入門
データサイエンスには不可欠の知識なので、この章を読んで眠くなるのでは始まらないです。頑張って読み切りましょう。
第2部『会計データサイエンスの実践』では、いくつかの実務的なユースケースをもとに、動作するPythonコードを用いての解説が続きます。
第4章 監査で使われる統計的サンプリングツールを実装しよう
第5章 会計データの特徴を理解して将来の売上を予測しよう
こちらの章は個人的に一番楽しく読みすすめられました。帰無仮説をはじめとする統計的サンプリングの解説を、コードまで落とし込んで解説した画期的なパートだと思います。季節変動のある売上データに基づく将来売上予測、というわかりやすいユースケースから、SARUMAモデルによる予測を解説。こちらも動作するコードで解説をわかりやすく表現していて、概念的な解説をより腹落ちしやすく伝える工夫が随所に見られました。
なお、統計的サンプリングについては発行年月は古いですがこちらの良書があるので、併せて参照するのがよいでしょう。

第6章 会計データを使って機械学習に挑戦しよう
会計データを使った機械学習への挑戦。機械学習の基本解説から、よりリアルなケースとしてたこ焼き屋の会計帳簿をもとにさまざまな分析からはじまり、決定木による顧客行動の分析やSVMによる掛け売り予測と資金繰り対応という実践的なテーマで分析を試みます。ここでも概念的な説明から実際のコードに落とし込むことで理解が容易な説明になっています。
第7章 会計データの異常検知をしよう
異常検知の問題設定にはじまり、正規分布に基づく異常値分析の解説です。この章で難易度が一気に上がりますが、会計監査の実務ではお馴染みのトピックを取り上げているので読み切りたいところです。深層学習の話題にも少し触れているのが興味深いですね。
第8章 データサイエンスを意思決定に活用しよう
ベイズ統計モデルによる不確実性モデリングや、自己回帰モデルによる在庫予測の解決、ロジスティック回帰モデルによる貸倒予測、生存時間モデルによる将来キャッシュフローの予測など、実践的な意思決定に用いるためのデータ分析がとりあげられています。サブスクリプション事業ではおなじみの離脱予測などのユースケースがあるので、SaaS企業の参考にもなるでしょう。こちらもコード盛りだくさんで消化不良になりそうですが、実際に動作させながら確認していくと面白さを味わえます。
第9章 データ分析基盤を構築しよう
会計データの特徴に始まり、効果的なデータ分析基盤の構築指針について解説しています。永遠のテーマではありますが、『データを何のために使うか』という根本的な問いかけは、データサイエンスに欠くことのできないものです。こちらも丁寧な解説が行われています。
参考文献それぞれに一言コメントがあるのがよいですが、章によってなかったりとばらつきがあるのは少し残念でした。複数著者だと符丁を合わせるのが難しいですね。
全体的に、会計データサイエンスの視点を掘り下げつつ実践的に理解したい方には格好の入門書だと思いますので強くおすすめいたします。本書はPythonやデータ分析の入門向けなので、より突っ込んだ深層学習や昨今のトレンドである生成AIにからめた解説触れていない点については、今後の続編に期待したいと思います。
なお、オビ部分にちょっとした遊び心があるので、実際に手に取って確かめてみましょう。
【セミナー】サステナビリティ開示とサイバーセキュリティ 2023/05/18
月曜日 , 22, 5月 2023 未分類 【セミナー】サステナビリティ開示とサイバーセキュリティ 2023/05/18 はコメントを受け付けていません
DNPエグゼクティブセミナーにて、サステナビリティ開示とサイバーセキュリティについて登壇いたしました。当日のセミナー資料をアップロードしましたので、ご笑覧ください。
タイトル:
DNPエグゼクティブセミナー
サステナビリティ開示とサイバーセキュリティ~いまから考えるべきこと~
日時:
2023年05月18日
当事務所のサービスご案内はこちらです
https://harakancpa.com/
[専門情報]経営研究調査会研究報告第70号「スタートアップ企業の価値評価実務」の公表
木曜日 , 6, 4月 2023 未分類 [専門情報]経営研究調査会研究報告第70号「スタートアップ企業の価値評価実務」の公表 はコメントを受け付けていません
日本公認会計士協会より、2023/04/04に以下文書が公表されました。
経営研究調査会研究報告第70号「スタートアップ企業の価値評価実務」の公表について
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20230404fbe.html
本文書の目次は以下のとおりです。
Ⅰ スタートアップ企業の動向と各種団体の対応
Ⅱ スタートアップ企業の価値評価の動向
Ⅲ スタートアップ企業の価値評価上の特徴と留意点
Ⅳ スタートアップ企業の株主価値評価
Ⅴ スタートアップ企業が種類株式を発行する場合の株式価値評価
Ⅵ スタートアップ企業の評価例
Ⅶ スタートアップ企業の価値評価を会計目的で実施する場合の留意点
Ⅷ 進化するスタートアップ企業の資金調達と評価上の対応
Ⅸ スタートアップ企業の価値評価を巡る課題と留意点
Ⅹ 価値評価業務の参考となる文献と用語集
「Ⅴ スタートアップ企業が種類株式を発行する場合の株式価値評価」「Ⅵ スタートアップ企業の評価例」には、事業計画とFCFのモデルケースによる株式価値評価の記載があります。このフェーズの株式価値評価のプロセスをコンパクトにまとめた資料として、一読をお勧めします。
当事務所のサービスメニューはこちらです
[記事掲載]Tech Target Japanに『「電子取引データ保存の義務化」に向けた準備と運用』第4回が掲載されました
水曜日 , 29, 3月 2023 未分類 [記事掲載]Tech Target Japanに『「電子取引データ保存の義務化」に向けた準備と運用』第4回が掲載されました はコメントを受け付けていません
Webメディア「Tech Target Japan」に連載記事
『「電子取引データ保存の義務化」に向けた準備と運用』
第4回の記事が掲載されました。会員限定コンテンツですが、無料登録すると最後まで読めます。
電子帳簿保存法改正の解説で、5回シリーズになります。
今回は電子取引データの該当性について解説しております。お手すきのときにご笑覧ください。
「電子取引データ保存の義務化」に向けた準備と運用【第4回】
これは「電子取引」に該当する? 4つの“ありがちなケース”で解説
https://techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/2301/16/news01.html
第1回:2022年改正電子帳簿保存法を改正前と比較、「4つの変化」とインパクト
第2回:どれが「電子取引」? 電子帳簿保存法改正の意外な落とし穴
第3回:始める前に要チェック 違法にならない「電子取引データの保存環境」とは
当事務所のサービスメニューはこちらです
[記事掲載]Tech Target Japanに『「電子取引データ保存の義務化」に向けた準備と運用』第3回が掲載されました
木曜日 , 2, 2月 2023 未分類 [記事掲載]Tech Target Japanに『「電子取引データ保存の義務化」に向けた準備と運用』第3回が掲載されました はコメントを受け付けていません
Webメディア「Tech Target Japan」に連載記事
『「電子取引データ保存の義務化」に向けた準備と運用』
第3回の記事が掲載されました。会員限定コンテンツですが、無料登録すると最後まで読めます。
電子帳簿保存法改正の解説で、5回シリーズになります。今回は電子取引データの保存環境要件について解説しております。お手すきのときにご笑覧ください。
「電子取引データ保存の義務化」に向けた準備と運用【第3回】
始める前に要チェック 違法にならない「電子取引データの保存環境」とは
https://techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/2212/09/news15.html
第1回:2022年改正電子帳簿保存法を改正前と比較、「4つの変化」とインパクト
第2回:どれが「電子取引」? 電子帳簿保存法改正の意外な落とし穴
当事務所のサービスメニューはこちらです
明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

2022年も、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大の影響は収束することなく、引き続き試練の多い年となりました。従来どおりの感染対策を継続しつつ、社会経済を維持していくストレスとしばらく付き合っていくことになりそうです。
テレワーク(リモートワーク)スタイルと出社スタイルの共存が模索されるなか、生産性を維持しつつ働きやすい環境作りが追求されてきた一年と感じます。われわれの社会は今後どのような方向を目指して進んでいくのでしょうか。
2022年に上梓した拙著「経理のテレワーク 第2版」では、財務経理業務におけるテレワークの方向性について、私なりに展望を述べておりますのでご笑覧いただければ幸いです。
2023年は先行きに不安を抱えつつも、新たな挑戦を積極的に行い、実績を挙げ、成長を求めていきたいと思います。弊事務所は引き続きお客様の成長に寄り添いつつ、その成長に向けてさまざまな施策を講じます。個人としても、引き続きスキル向上に精進する所存です。
メンバー一丸となって本年も邁進して参りますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
クレタ・アソシエイツ 原幹公認会計士事務所 代表
公認会計士・税理士・公認情報システム監査人(CISA)・公認不正検査士(CFE)
原 幹
お問い合わせはこちらまで
2023年(令和05年)12月までの税務カレンダー(Googleカレンダー形式)を更新しましたのでお知らせします。

PC/スマホ/タブレット等でご利用ください。更新内容は以下のとおりです。
- 2023年1月-12月の項目を追加
基本的に毎年同じイベントですが、休日による変動を調整しています。
表示イメージは以下のとおりです。項目をクリックすると詳細が表示されます。カレンダー右下の「+」ボタンを押して、ご自分のカレンダーに追加することもできます。ご利用は自己責任にてお願いいたします。
URLはこちら(うまく表示できない場合はブラウザでコピー&ペーストしてください)
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=harakancpa.com_2qhjtrecvq75rb5rjed2nlfnfo%40group.calendar.google.com&ctz=Asia%2FTokyo(Google Chromeを推奨。環境によっては見えないことがあります)
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=harakancpa.com_2qhjtrecvq75rb5rjed2nlfnfo%40group.calendar.google.com&ctz=Asia%2FTokyo2022年は政情不安や為替不安定など不安定が続く一年でした。2023年は改正電子帳簿保存法やインボイス制度の本格的な施行に向けて、企業の対応に追われる日々は続くものと予想されます。経理・財務・税務領域のデジタル化・デジタルを前提とした仕事を再設計するニーズを満たせるように、当事務所はバックオフィスの効率化を志向するお客様をこれまでどおりに引き続きご支援して参ります。
以上、本年最後の投稿になります。
2022年もお世話になりました。来年も良い一年でありますように。
当事務所へのお問い合わせはこちらまで。カレンダーへのご要望もお待ちしております。